希少な『トンネル内に作られた商店街』
隧道マーケットとは、トンネルに沿って作られた商店街です。
昭和炭鉱の隧道マーケットはトンネルの片側に多数の商店が並んでいました。
昭和炭鉱は北海道の沼田町に1930年から1969年まで採掘をおこなっていた炭鉱。
かつてあった集落は消え、今は山奥の何もないような場所になっていますが、炭鉱があった当時は4000人ほどが生活する集落が形成されていました。
そんな炭鉱街の、昭和炭鉱で働く人とその家族の生活を支えていたのがトンネルに並ぶ商店街、隧道マーケットなのです。

昭和炭鉱とは? – 沼田町の繁栄を支えた柱 -(1930年~1969年)
創生と発展
昭和炭鉱の歴史は、明治31年(1899年)の試掘に始まり、大正7年(1918年)には明治鉱業株式会社の所有となりました 。本格的な出炭が開始されたのは昭和5年(1930年)であり、これは石炭輸送に不可欠な留萠鉄道の全線開通と軌を一にするものでした 。この鉄道は、産出される石炭を積出港や消費地へ運ぶ大動脈であると同時に、物資や人々を炭鉱町へともたらす生命線でもありました 。
産出される石炭は良質で、工業用燃料や一般家庭の暖房用として広く利用されました 。軍艦島で産出された「強粘結炭」のような特殊な高品位炭であったかは記録からは明確ではありませんが 、産業用途に適していたことは確かです。
最盛期の様相
昭和炭鉱が最も活況を呈したのは昭和23年(1954年)頃で、この時期には約3,800人から4,000人の人々が生活する集落が形成されていました 。年間出炭量はピーク時で約22万9千トンに達し 、閉山までの総生産量は約500万トンを記録しています 。
この炭鉱は、沼田町の経済を牽引する存在であり、炭鉱労働者は比較的高い賃金を得ていました。その結果、地域経済は潤い、多くの商店が軒を連ねるなど、活気に満ちた町が形成されました 。長期間にわたり、雨竜炭田の中でも最も安定した操業を続けていたとされています 。
炭鉱の影に生きた人々の暮らし:賑わいのコミュニティ
昭和地区は、単なる労働者の居住地ではなく、一つの完結した都市機能を備えていました。社宅(「炭住アパート」とも呼ばれる )に加え、小中学校、病院、郵便局(昭和6年開局、昭和44年廃局 )、自家発電所、製材工場などが整備されていました 。ポロピリ湖展望台にあった地図には、小中学校や住宅が道路沿いに配置されていた様子が示されています 。炭鉱住宅には等級があり、一般職員から管理職に至るまで、住居にも格差が存在したことが窺えます 。
このような炭鉱町における社会構造の中で特筆すべきは、「友子会」の存在です。友子会は、炭鉱の開坑時から設立された互助組織で、病気、怪我、冠婚葬祭などの際に互いに助け合い、また採炭技術の伝承も行うという、炭鉱社会独特の制度でした 。しかし、戦後の労働組合の誕生による二重加入の負担増や社会保障制度の充実、そしてその封建的な側面から、昭和30年(1955年)頃には解散しています 。この友子会の解散は、閉山より十数年も前の出来事であり、閉鎖的な炭鉱町にも戦後日本の社会構造の変化の波が及んでいたことを示しています。伝統的な相互扶助から、より近代的で権利に基づいた労働関係や公的な社会保障へと移行していく過程が、この isolated community の内部でも進行していたのです。
当初、この隔絶された炭鉱町への交通手段は留萠鉄道のみであり、自動車が通行可能な道路は存在しませんでした 。この地理的条件が、後述する隧道マーケットのような独自の生活様式を生み出す一因ともなりました。
昭和炭鉱を中心としたコミュニティは、資源開発という単一産業に依存して急速に発展しましたが、その繁栄は石炭という資源の価値と可採性に完全に左右されていました。学校や病院といった恒久的な社会基盤の整備は、鉱業会社や行政による一定の長期的な展望があったことを示唆しますが、結果として炭鉱の終焉は町の消滅に直結しました 。これは、資源依存型都市に共通する盛衰のサイクルと、産業構造の転換がもたらす社会的な変容の典型例と言えるでしょう。
避けられぬ衰退と閉山(1969年)
昭和炭鉱の繁栄は永遠には続きませんでした。主な要因は、1960年代における国のエネルギー政策の転換、すなわち石炭から石油へのシフトでした 。政府は昭和37年(1962年)及び昭和43年(1968年)に石炭政策を発表し、このエネルギー転換を加速させました 。
これに加え、操業上の問題も顕在化しました。炭層における断層の増加により出炭量が減少し、採算性が悪化したのです 。他の炭鉱の事例では、「安全に採掘し得る石炭が枯渇し、採掘可能な石炭を全て取り尽くした」ことが閉山の直接的な理由とされることもありますが 、昭和炭鉱の場合は、この採掘条件の悪化とエネルギー政策の転換が複合的に作用したと考えられます。
これらの結果、昭和炭鉱は昭和44年(1969年)にその長い歴史に幕を閉じました 。炭鉱と運命を共にした留萠鉄道も、その2年後の1971年に全線廃止となっています 。
隧道マーケットの現状
出入り口側の天井は低く、中に入ると天井が一段高くなります。
隧道マーケットは入り口が二つあったのですが、現在は片側は土砂崩れで通行できない様です。
そちら側の内部は出入り口から水が排出されずに水没してしまっています。
どの様なお店があったのか?
現地で確認できた残留物は、お菓子のケース、ガラナなどのジュース類のビン、呉服店の看板、鮮魚輸送用の発泡スチロールと冷蔵ショーケース。
食料品がメインであった様ですが、呉服屋なんかもあったんですね。

親に手を引かれて隧道を訪れた子供もたくさんいたのでしょう。
隧道マーケットで買ってもらったたくさんのお菓子。
きっといい思い出。





最後まで隧道マーケット守りたかった人々のメッセージ。
周囲は深い森に囲まれた地帯。
昭和炭鉱は守りたいほど良い場所であったのだろうか?






宮向呉服店の看板。





トンネル内部は完全な暗闇に包まれており、探索には強力な光源が不可欠。煉瓦積みの壁面は各所で崩落し、天井からの落石の危険も絶えず存在します 。空気はひんやりと湿っており 、トンネルの一方の坑口は土砂崩れで完全に埋没しているため排水が悪く、内部は水没している箇所もあります。
このような過酷な状況にもかかわらず、隧道マーケットの内部には、地上の廃墟群とは対照的に、かつての商業活動を偲ばせる多くの遺物が比較的良好な状態で残存しています。店舗の看板 、商品棚 、魚屋で使われたと思われる冷蔵陳列ケース 、昭和35年(1960年)製の電力メーター などが確認できます。特に注目すべきは、閉山に反対する当時のビラや貼り紙が残っていることであり 、これは炭鉱コミュニティが直面した最後の苦闘を生々しく伝える貴重な資料なのです。
地上施設が風雪や植物の侵食により急速に風化していくのに対し、隧道マーケット内部は地下という特殊な環境によって、より繊細な物質(紙類や木製品など)が長期間保存されやすい条件にあったと考えられます。地上の巨大な産業遺構が炭鉱の規模や生産プロセスを物語るのに対し、隧道マーケットの遺物は、そこで暮らした人々の日常生活や感情をより直接的に伝えてくれます。この「タイムカプセル」効果こそが、隧道マーケットを特異な存在たらしめている要因の一つです。
隧道マーケットとは? – 厳寒の気候への独創的な適応 –
以下のサイトに、当時の隧道マーケットの写真が2枚だけ掲載されています。
トンネル内にある以外は、普通の昭和の商店ですね。
構想と論理的根拠:自然の挑戦への応答
昭和炭鉱が位置した北海道沼田町は、年間累積降雪量が10メートルを超えることもある日本有数の豪雪地帯です 。このような厳しい気候条件下では、冬季の外出や日常的な商業活動は著しく困難となります。
この自然の挑戦に対する独創的な解決策として考案されたのが、「隧道マーケット」でした。これは、文字通りトンネル(隧道)の内部に商店街を設けるというもので、降雪や厳寒の影響を受けずに人々が買い物や交流を行える空間を提供することを目的としていました 。この隧道マーケットは、単に商業的な利便性を追求しただけでなく、過酷な自然環境下でコミュニティの機能を維持し、住民の生活の質を高めるための重要な社会基盤としての役割を担っていたと考えられます。このような厳しい環境への適応策は、住民の結束力を高め、孤立しがちな冬季における精神的な支えともなったことでしょう。
雪害対策としてトンネル内に商店街を建設するという試みは、世界的に見ても極めて稀有な事例であると指摘されています 。
建築的独自性と構造
隧道マーケットは、専用に掘削されたトンネルの片側に店舗スペースを設ける形で建設されました 。現存する遺構の状況から、トンネルは煉瓦積みであったことが確認されていますが、経年劣化により崩壊の危機に瀕しています 。
内部は、約10軒ほどの店舗が直線的に並ぶレイアウトでした 。このような大規模な地下構造物を建設し、商店街として機能させたという事実は、当時の昭和炭鉱コミュニティが一定の永続性を見込んでいたことを示唆しています。一時的な仮設の集落であれば、これほど大掛かりで恒久的な施設への投資は行われなかったでしょう。隧道マーケットの存在は、鉱業会社や地域計画者が、炭鉱の長期的な操業と、それに伴う安定したコミュニティの維持を目指していたことの証左と言えます。
過去への窓:商業とコミュニティ生活
隧道マーケットには、魚屋や呉服屋といった、当時の一般的な町の商店街に見られるような多様な店舗が軒を連ねていました 。ここは、住民たちが天候を気にすることなく日々の必需品を求め、また、自然発生的に人々の交流が生まれる場として機能し、特に長く厳しい冬の間、コミュニティの結束を維持する上で不可欠な役割を果たしたと推察されます 。
この隧道マーケットは、「全国的にも珍しい」施設として、その歴史的・文化的価値が高く評価されています 。
崩壊しつつある隧道マーケット


昭和炭鉱と隧道マーケットの廃墟は、その物理的な姿が薄れつつあるとしても、日本の歴史における重要な一時期を照らし出す貴重な証人です。それは産業の野心、コミュニティの適応力、そして時の流れの非情さを静かに物語りながら、私たちに過去を振り返り、未来を考えるための深い洞察を与え続けています。これらの遺構から学び取れる教訓は、単に過去を懐かしむことに留まらず、現代社会が直面する様々な課題、例えば地域社会の持続可能性やエネルギー転換の社会的影響などを考える上でも、示唆に富むものと言えるでしょう。
大量のコウモリのすみか
昭和炭鉱隧道マーケット内部の現在は大量のコウモリの住処になっています。
100匹以上生息し、内部を飛び交います。
隧道内に入るのをためらう程に、バサバサと飛び回り、近づくと正面から向かってきます。


昭和炭鉱 隧道マーケットへの行き方
道道867号線からの分岐地点から少し入るとゲートがあり、そこから徒歩になります。
距離3.6km。
ゲートから入った後は、道の跡がありそれに沿って歩きます。
約3キロほどいくと分岐地点があります。
左折方向が完全に草に覆われわかりにくく、道の跡は右方向にしか伸びていません。
ここを間違えると変な方向に向かってしまいます。
詳細は動画を見ていただくと分かりやすいです。
実際に行ってみて確認したのですが、過去に崩落などが起きていた通行が困難とされていた橋が、修復されて使えるようになっています。
動画を見ていただくと分かりやすいのですが、所々車が通った形跡も残っていました。
道に沿って、草も刈られています。
道路は整備されているようです。
ただ、ゲートは閉まっているので車では通れません。
道は整っていますので、マウンテンバイクなどがあれば、分岐地点までは楽に行けると思いました。
分岐地点の後の昭和炭鉱方向への道は、手入れされておらず、完全にジャングルと化しています。
そこからは、徒歩が早いです。
草木に埋もれている隧道マーケット入口前
現地に到達しても、隧道マーケットの入り口を探すのは困難です。
当時、隧道マーケットに行くには小川を超える小さな橋があったようで、その残骸を探すと隧道マーケットの入り口を探しやすいです。
以下の360度画像は隧道マーケット入り口の少し手前で撮影したものです。
小川を越えた向こう側に、隧道マーケットの入り口がわずかに見えます。
昭和炭鉱 隧道マーケット跡の詳細情報
| 所在地 | 北海道雨竜郡沼田町浅野 |
| 携帯電話 | 圏外 |

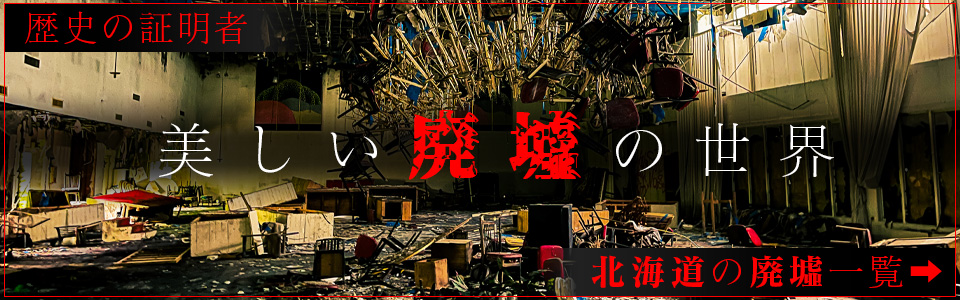
![昭和炭鉱 隧道マーケット跡 [北海道雨竜郡沼田町]](https://touring.hokkaido.world/wp-content/uploads/2021/10/昭和炭鉱-隧道マーケット-08.jpg)


当サイトの掲載画像使用に関して
当サイトの掲載画像は、フリー素材としてご使用いただけます。
詳細は以下ページよりご確認下さい。