北海道山奥で朽ち果てる一つの歴史 昭和29年閉山 浦幌炭鉱
北海道十勝群浦幌町炭山
帯広市と釧路市の中間の山奥にかつてあった浦幌炭鉱。
昭和29年に閉山。
当時は周辺は一つの街が出来上がり、730戸の炭鉱住宅があり3600人が生活をしていました。
小、中学校の他、近隣の池田高校の定時制の分校も建てられました。
1967年昭和42年、常室小学校、常室中学校の分校が廃校になると共に、炭鉱住宅街から人々は姿を消しました。
失われた町の囁き – 浦幌炭鉱、静寂なる心の残影
北海道の空の下、朽ち果てようとする栄町アパート群は、蔦に覆われ静寂の中に佇んでいる。風の音か、野生動物の気配だけが時折その沈黙を破る。浦幌炭鉱跡は、単なる崩れゆく建物群ではない。それは人間の努力、共同体、そして最終的には時間と自然への降伏が幾重にも刻まれたパリンプセストなのである。二棟のアパートが見え、手前の棟の壁は白く、向こう側は茶色を呈し、どちらも樹木に覆われ、自然と一体化しつつある。この光景は、始まりの印象を強く刻む。
日本の石炭産業の興亡という国家的な物語の中で、浦幌炭鉱の物語は、この大きな歴史における痛切な地方の一章として位置づけられる。北海道がこの産業において果たした重要な役割は言うまでもない。本稿では、繁栄の儚さ、記憶の強靭さ、そして朽ち果てたものの中に見出される妖しい美しさ(「滅びの美」)。
浦幌の物語は、戦後日本の経済的軌跡の縮図でもある。資源ベースの工業化から新エネルギー源への転換、そしてそれに続く単一産業の町への社会的影響である。炭鉱の操業と最盛期は、日本の戦後復興と産業成長と軌を一にする。1954年の閉山 は、石炭からの全国的なエネルギー政策の転換の始まりを反映している。学校閉鎖後の完全な放棄は、機能しなくなった産業に結びついたコミュニティの社会的崩壊を示しており、このパターンは多くの炭鉱町で繰り返された。
黒いダイヤモンドの約束:浦幌炭鉱の創生と最盛期
A. 常室谷における鉱業の夜明け
浦幌における石炭採掘の歴史は、1918年(大正7年)、町内を流れる常室川(とこむろがわ)の上流で始まった。これが事業の誕生を印す。初期の開発では、常室、留真(るしん)、毛無(けなし)といった坑口が設けられ、当初は毛無が主要な出炭地であったとされる。留真坑は1933年(昭和8年)に再開された。その後、双運坑(そううんこう)と太平坑(たいへいこう)が開発され、石炭は当初、馬車で浦幌市街まで運ばれていた。
B. 三菱時代と産業の隆盛
昭和11年(1936年)10月、三菱雄別炭砿鉄道株式会社が浦幌炭鉱を買収し、山向こうの音別町尺別炭砿の管轄下に置かれた。これは、操業規模と統合における大きな前進を意味した。浦幌と尺別選炭所を結ぶ重要なインフラである尺浦通洞(しゃくうらつうどう)は、全長6キロメートルに及ぶこのトンネルが昭和16年(1941年)11月に開通し、それまで索道で行われていた石炭輸送の近代化が図られた。このトンネルは、炭鉱がより大きな産業ネットワークに統合されたことを象徴している。地理的には、浦幌は釧路炭田の西端に位置していた。
浦幌炭鉱は孤立した存在ではなく、特に三菱による買収と尺浦通洞の建設後は、より大規模な尺別炭鉱と操業上・物流上密接に結びついていた。これは、三菱が石炭層を効率的に採掘するための地域戦略を示唆している。尺浦通洞は尺別の選炭工場への輸送のために建設されたことから、浦幌が供給炭鉱であったことがわかる。この依存関係は、浦幌の操業ライフサイクルと最終的な閉山を理解する上で極めて重要である。
C. 絶頂期へ – 生命力に脈打つ町
最盛期には、浦幌の炭鉱町は約3,600人の人々が暮らす活気あるコミュニティであった。この数字は、賑やかで密集した集落の姿を映し出す。炭鉱は第二次世界大戦中に一時休坑を経験し、昭和19年(1944年)には国策による一時休山が行われ、1,000人の鉱夫が家族をこの地に残して九州へ送られた。戦後は再興し、昭和24年(1949年)までには鉱夫の数が戦前の水準に戻り、朝鮮戦争特需もあって生産量は伸びた。
三菱鉱業(後の三菱マテリアル)による広範な地域社会インフラの開発(詳細は次章で述べるが、その萌芽はここにある)は、「企業城下町」モデルを示している。このモデルでは、企業は雇用だけでなく、住宅や社会サービスも提供した。これにより、強力で自己完結的なコミュニティが形成されたが、同時に企業の盛衰に大きく依存するコミュニティでもあった。3,600人という町の規模や、学校、病院などの整備は、企業主導の開発を意味する。三菱による所有は、町を監督する企業構造を示唆している。炭鉱閉山後の急速な衰退は、この依存関係を浮き彫りにしている。
浦幌炭鉱とそのコミュニティの略年表
| 年代 | 出来事 |
| 1918年(大正7年) | 常室川上流で石炭採掘開始。毛無、常室、留真に坑口設置。 |
| 1933年(昭和8年) | 留真坑再開。双運坑、太平坑開発。 |
| 1936年(昭和11年)10月 | 三菱雄別炭砿鉄道株式会社が買収。尺別炭鉱の管轄下に入る。 |
| 1941年(昭和16年)11月 | 尺浦通洞(浦幌~尺別間)開通。 |
| 1944年(昭和19年) | 戦時下の一時休山。鉱夫1,000名が九州へ送られる。 |
| 第二次世界大戦後 | 操業再開、朝鮮戦争特需。 |
| 1950年代初頭(最盛期) | 人口約3,600人。町内施設整備。 |
| 1953年(昭和28年) | 栄町アパート建設。 |
| 1954年(昭和29年)10月 | 浦幌炭鉱閉山。従業員384名配置転換。 |
| 1967年(昭和42年)7月 | 常室小中学校炭鉱分校廃校。残っていた住民が地区を離れる。 |
石炭に刻まれた生活:栄町アパートと鉱山コミュニティ
A. 栄町アパート – 荒野の我が家
「栄町アパート」と呼ばれるこれらの住居群は、昭和28年(1953年)頃に建設され、当初は主に独身労働者のための寮として利用されていた。コミュニティの成長に伴い、後には家族も居住したと考えられる。3つの主要なアパートブロックがあり、鉄筋コンクリート造りで、崩れたモルタルの下にはレンガやブロック積みの壁が見える。一部の窓には「モダンな趣」があったとされ、建物は堅牢で、山中に「団地」を形成していた。一部屋の広さは約30平方メートルであった。
これらのアパート群は、当時としては「モダン」であり、山中に「団地」を形成していたこと、そして映画館のような施設があったことは、僻遠で厳しい山岳環境に都市的な利便性をもたらそうとする試みであった。これは企業城下町の重要な側面、すなわち、そうでなければ魅力のない場所に労働力を引きつけ、維持するためにアメニティを提供するという点を浮き彫りにしている。「人里遠く離れた深い山の中」にこのような複合施設を見出すことの「非現実感」は、この構築された現実を物語っている。
B. 自己完結した世界 – 日常生活の織物
炭山地区には、730戸の世帯が暮らしていたとされ、小学校、中学校、病院、警察、神社・寺院、そして郵便局(常室簡易局)まで備わっていた。
アパートの道を挟んだ向かいには、地域社会の拠点であった協和会館があり、毎日映画が上映されていた。昭和30年(1955年)頃の少女雑誌「マーガレット」の断片や、柱に貼られたアニメキャラクターのシールといった発見は、かつてそこで暮らした子供たちや家族との具体的な繋がりを感じさせ、廃墟に人間味を与えている。これらの小さな遺物は、この一時的なコミュニティで育った子供たちの存在を強く示している。彼らの子供時代は、厳しい産業を背景に、その産業に完全に依存した町で過ごされた。これらの遺物は、この場所の産業的性質とは対照的に、そこにあった家庭生活や個人的な生活を浮き彫りにする。
浦幌炭鉱町の主要施設(最盛期)
| 施設種類 | 具体的内容 |
| 住宅 | 栄町アパート(3棟、独身寮/家族用)、炭山地区全体で約730世帯 |
| 教育 | 常室小学校炭鉱分校、常室中学校炭鉱分校 |
| 医療 | 病院 |
| コミュニティ・娯楽 | 協和会館(集会所、毎日映画上映) |
| サービス | 警察、郵便局(常室簡易局)、商店(「町」の存在から推測) |
| 宗教施設 | 神社・寺院、山神社 |
C. 炭鉱の影のコミュニティと文化
生活は炭鉱のリズムを中心に展開していた。コミュニティは、共通の仕事と相対的な孤立によって育まれた、固い絆で結ばれていたであろう。労働者には「僻地手当」が支給されていたという記述は、その厳しい環境を示唆している。後に浦幌神社に移築された「山神社」や「乳神神社」の存在は、コミュニティの精神的、民俗的な信仰を物語っている。
長い別れ:衰退、閉山、そして消えゆく灯火
A. 変化の囁き – エネルギー潮流の転換
1950年代半ばから、日本のエネルギー政策が石炭から石油へと大きく転換し始めたことが、全国的な背景として挙げられる。これは浦幌の衰退の舞台を設定した。朝鮮戦争特需後の「反動不況」も、もう一つの要因であった。
B. 1954年10月 – 一時代の終焉
浦幌炭鉱は1954年(昭和29年)10月に正式に閉山した。これが決定的な転換点であった。384人の従業員が影響を受け、多くは雄別、尺別、茂尻といった他の三菱系炭鉱へ配置転換された。これは人的コストと離散を浮き彫りにしている。この384人の従業員の異動は単なる統計ではない。それは、家族が根こそぎにされ、社会的ネットワークが断ち切られ、自分たちのコントロールをはるかに超えたマクロ経済の力によって人生が方向転換させられたことを意味する。これは、産業衰退の見過ごされがちな人的側面を強調している。
C. ゆっくりとした消失 – 町は空になる
炭鉱は1954年に閉山したが、林業などに従事していた一部の住民は残っていたようである。常室小中学校炭鉱分校が昭和42年(1967年)7月に閉校したことが、しばしば小さな孤立したコミュニティにとっての弔いの鐘となる。この出来事は、最後の家族の離散を印した。学校閉鎖後、炭山地区からは全ての住民がいなくなったと記録されている。
閉山の1954年が主要な経済的ショックであったが、町は一夜にして死んだわけではなかった。1967年の学校閉鎖まで一部の住民が残っていたことは、より緩やかで痛みを伴うコミュニティ解体のプロセスを示唆しており、おそらく一部の人々は希望を持ち続けたり、移転の選択肢が限られていたりしたのだろう。学校の閉鎖は、決定的な社会的終焉であった。1954年の炭鉱閉鎖と、1967年の最終的な学校閉鎖・住民退去との間の13年間の隔たりは、即時放棄ではなく衰退期があったことを示している。
自然の再生:現在の栄町アパート – 崩壊と成長のシンフォニー
A. 「滅びの美」 – 無常の美学
現在のアパート群は、白と茶色の壁が木々に絡まれ、モルタルが剥落してレンガやブロックが露わになり、屋上にはエゾマツのような成木が生い茂っている。自然のゆっくりとした、しかし執拗な再生の力強いイメージは、「建物と樹木が、自然な姿で一体化する光景」として捉えられている。侵食する植物の緑と朽ち果てていく人工構造物のコントラストは、時に季節の色、緑の草地に対する黄葉などによって際立つ。
これらの廃墟は、伝統的な意味での遺産として正式に保存されているわけではないが、意図せざる過去の時代の記念碑となっている。その崩壊そのものと、自然がそれらと相互作用する様は、産業史とその余波に対する強力で生き生きとした証であり、修復された場所よりも一部の人々にとってはるかに示唆に富むものとなっている。崩壊と自然再生の詳細な描写は、現在のアイデンティティの中心である。「滅びの美」という言葉は、その廃墟の状態から派生するこの美的かつ感情的な力を凝縮している。
B. 時の抱擁を巡る – 廃墟の感覚的詳細
「半世紀もの間、誰も訪れないままに、静かに時を過ごしてきた」という雰囲気は、時が止まったかのような場所(例えば、昭和37年(1962年)から手つかずのように見える部屋)を想起させる。内部は基礎が露出し、床はなくなり、障子の残骸が見られ、木製の窓枠は劣化している。打ち捨てられた酒瓶やコップといった生活の痕跡も残る。
周辺には、冷泉が湧き出る水没した排気坑、病院の基礎、鉄道インフラの残骸(橋台)、換気口など、他の遺構も点在する。常室川自体もその痕跡を留めており、頁岩の川岸は石炭と関連があるかもしれない。
C. 感じられる静寂 – ゴーストタウンの妖しい存在感
圧倒的な放棄の感覚と自然の力。「人里遠く離れた深い山の中」 にこのような構造物を見出すことの「非現実感」。そして、「自然に還る様子と、劣化の風景が物悲しい」と表現される、崩壊の哀愁を帯びた美しさ。
静寂の中の残響:遺産、記憶、そして浦幌の過去の魅力
記憶を生き続ける – 浦幌町立博物館の役割
博物館は歴史の保存に積極的に取り組み、特に炭鉱閉山70周年を記念した特別展(2024年7月~9月)を開催した。また、博物館は現地へのツアー(「旧浦幌炭鉱や留真温泉を巡る『森のルート』のツアーを実施」)や、北海道大学の鈴木里奈氏のような専門家を招いたシンポジウム「炭鉱遺産の保存と活用のいま」などを企画している。『浦幌町百年史』や博物館の刊行物などの歴史資料も、利用可能な歴史データを示唆している。
浦幌町立博物館による史跡の歴史をキュレーションし解釈する公式の取り組みと、「廃墟」愛好家や芸術家による非公式でしばしば非合法な探検との間には、興味深い相互作用が見られる。博物館が歴史的文脈と管理されたアクセスを提供する一方で、後者のグループは廃墟とのより直接的で媒介されない出会いを求めている。これは、そのような遺産を評価し、関与するさまざまな方法を示唆している。
芸術家と探検家のためのキャンバス – 「廃墟」の魅力
この場所は「廃墟マニア」の間で有名である。写真家・啝(Wataru)氏による写真集『廃墟幻想』には、浦幌のドローン空撮や星景写真が収められており、彼のInstagramアカウントは@neji_maki_doriである。廃墟の視覚的な力は、創造的な解釈を刺激する。
遺産についての考察 – これらの廃墟は何を意味するのか?
浦幌の廃墟は、北海道の産業の過去と、そこに織り込まれた人々の物語への具体的な繋がりである。このような場所の保存と自然崩壊をめぐる議論は、「炭鉱遺産の保存と活用のいま」と題されたシンポジウムでも触れられている。鈴木里奈氏が研究する元住民にとっての「故郷を目的地とする観光」は、これらの廃墟が記憶と失われたコミュニティの感覚をどのように呼び起こすかを示している。
哀愁を帯びた美しさと失われたコミュニティの物語を持つ浦幌の地は、「ダークツーリズム」や「情動的遺産」の要素に触れている。そこでは、感情的な共鳴と衰退の物語が魅力の一部となっている。「滅びの美」に焦点を当てることは、純粋に歴史的な評価ではなく、感情的な評価に訴えかける。鈴木里奈氏の研究は、これらの場所に戻ってきた元住民の記憶と感情に明確に焦点を当てており、この種の関与は単純な歴史的関心を超え、そのような場所の心理的および感情的な影響を掘り下げている。
「炭鉱遺産の保存と活用のいま」をめぐる議論は、地域社会や学者が浦幌のような産業遺構をどのように定義し、管理するかに苦慮していることを示唆している。これらは伝統的な記念碑ではないが、重要な歴史的・文化的価値を保持している。これは、産業、労働、さらには衰退の場所を含む、遺産の進化する理解を反映している。
浦幌の消えた夢の永続的な共鳴
浦幌のアパート群と炭鉱跡は、北海道の歴史のダイナミックな時代と消え去った生活様式への、力強く静かな証として残っている。人間の野心、産業サイクルの厳しい現実、そして自然の容赦ない力が絡み合っていることを強調する。この場所は、記憶、哀愁、そして魅了し続けるユニークで妖しい美しさの場所である。
浦幌の廃墟は、北海道の多様な景観のタペストリーに貢献し、時間、産業、そして人間の足跡について熟考を促す、異なる種類の「観光」を提供している。このような場所から私たちが学べること、それは回復力、喪失、そして大地と朽ち果てた建造物に埋め込まれた物語についてである。
この物語は閉鎖と崩壊の一つであるが、同時に変容の物語でもある。浦幌の地は、産業の中心地からゴーストタウンへ、そして今ではユニークな生態学的・文化的空間へと変貌を遂げた。その意味と価値は、自然、記憶、そして人間の解釈によって形作られ、進化し続けている。浦幌炭鉱アパート群の具体的な物語は、北海道の地方史に根ざしながらも、好況と不況、コミュニティの形成と解体、産業変化が人々の生活に与える影響、そして廃墟の哀愁を帯びた美しさといった普遍的なテーマと共鳴する。これにより、この場所は地理的な境界を超えた重要性を持つのである。
浦幌炭鉱 廃アパート群の詳細情報
| 所在地 | 北海道十勝郡浦幌町炭山 |
| 携帯電話 | 圏外 |

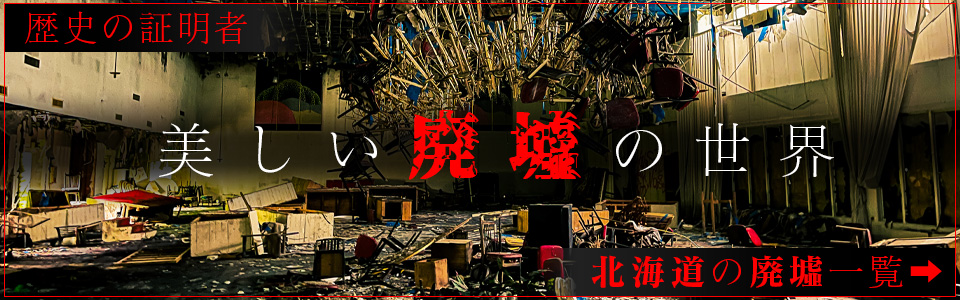



当サイトの掲載画像使用に関して
当サイトの掲載画像は、フリー素材としてご使用いただけます。
詳細は以下ページよりご確認下さい。